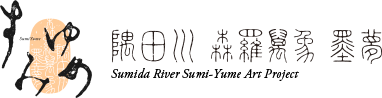見世物小屋の屋根裏で遊んでいる妖精や小悪魔ども ヒロセガイ・さわひらき 舟遊び 【2021年イベントレポート】

曳舟駅に降り立った。筆者にとって初めて来た場所だった。さわひらきが「舟遊び」と題し、かつての米屋の家屋で映像をインスタレーション的に展示すると聞き、それを見るためだった。
いかんせん、初めて訪れた場所だったので、当代では一般的なGoogle mapを活用し、目的地を入れ、その指示通りに歩いた。そのはずだったが、道すがら、何かに導かれるようにして、焼鳥屋さん、八百屋さん、魚屋さんなど、古くから地域に根差していると見受けられる商店を通りつつ、いつの間にか人が一人通れるような路地裏も通過することになり、展示に向かう片道だけでこの町の人気のない静かな昭和の佇まいを存分に体感することができた。
千葉で活動をした彫刻の名工・波の伊八の欄間掘り、その影響を受け描かれたとされる葛飾北斎の浮世絵《神奈川沖浪裏》、さらにこの北斎の傑作に触発され遠く海の向こうフランスで制作された印象派の画家クロード・モネの《舟遊び》。3人の、そして3つの作品にそれぞれ現れるレイヤーの連関に導かれて、さわひらきとヒロセガイは今回の展示のタイトルを「舟遊び」とした。
築60年余の古民家の屋根裏部屋という、普段は人が出入りすることのない場所で、今回、さわひらきは《envelope》(2014)、《absent》(2018)、《souvenir IV》(2012)、《for saya》(2011)の作品4点と、《magic lantern》、《wave》と題した未公開の映像素材の2点、計6点を用いたインスタレーションを構成した。さわひらきはこのインスタレーションで用いた映像の名前こそ教えてくれたが、家屋の中で映像はさまざまに配置され、断片化されており、映像をフラットに見せているものは1つとしてなかった。そのどれもが、家屋内のインスタレーションという全体の構成の素材として用いられていると思える展示であった。
われわれが生活のなかで体験する日常の記憶に、不意にアクセスする彼の映像。そこでわれわれの持つ記憶とさわひらきの映像とが共鳴し、われわれの日常が鮮やかに再生される。彼の創る映像体験に一貫した特徴である。鑑賞者の持つ記憶へとアプローチをし、その再構成を促す作品の構造は、今回のインスタレーションにおいてさらにその凄みを増している。今回の古民家を使った展示では、既存の米屋の家屋構成を存分に活かして作品を配置した結果、鑑賞者の展示空間での移動がかなり制限されている。特に今回は屋根裏部屋という、身を低くして、あたかも匍匐前進するような移動を強いられる狭い空間を活用しているが、そのことが鑑賞者に対して作品把握へのさらなる主体的な動きを促す。さわとヒロセが鑑賞者に対し、あえてそのような苦行を課すことによって、鑑賞者自らが選択したと思っている作品鑑賞の順序自体が、実は鑑賞者の意識しない遠い記憶と結びついているということ、そしてその遠い記憶がさわの映像によって呼び起こされていること、が、鑑賞者自身の体験において明示的になるのだ。
今回の映像でもそうだが、さわひらき作品の映像の中で言葉を発しない人物の像、言葉のない状況にあるからこそ、その存在を如実に見せてしまう人物の像は、その存在感ゆえに、実体が鑑賞者の記憶から切り取った残像に過ぎないものであることが露わになっている。そしてついには、”実”写とて鑑賞者の脳裏に映る何ものかに過ぎないことが露呈するのだ。われわれ鑑賞者は、さわの作品により開かれ繋がれた自身の記憶と、いままさに屋根裏という展示室で生じている体感との混在の中で、その心身に静謐な刺激を受けるだろう。さわひらきの作品により揺り動かされ、掬いあげられたわれわれの記憶。それは、鮮やかで新しくも懐かしさを感じる記憶として、再びわれわれに深く刻みこまれるだろう。
この展覧会を仕掛けたさわひらきとヒロセガイが鑑賞者に期待することは、いまここにある自分に対し、作品が日常に潜む自らの在り処を問いかける存在であると把握してもらうこと、そのことによって普段は意識しないもう1人の自分自身が日常の裏側に存在すると気づいてもらうこと、ではないかと筆者は考えた。元米屋の古い家屋に設置された二つのミラーボールから発せられる光の世界の中で、さわひらきと鑑賞者は、お互いの記憶を重ね合わせ、日常と非日常との境界を行き来しつつ、日常の自分と非日常の自分との境界、そして他者と自分の境界を改めて見つけ出す。屋根裏という非日常空間と、家屋の部屋という日常空間とをつなぐ梯子はヒロセガイが制作したものであり、さわの作品と鑑賞者、そして日常と非日常の重要な橋渡しとなっている。このように、今回の展示は要所でさわとヒロセとの共同作業の様子が垣間見え、ヒロセの制作物がさわの作品配置の実現に無理なく半肩担いでいるところに、今回の展示の現場性が感じられた。
さわひらきの映像作品に登場する様々なキャラクターについて、かつて筆者は「百鬼夜行」、「付喪神」に見立てた論考を書いたことがある。この屋根裏という、いかにも妖精や小悪魔、そして妖怪たちが介在しそうな場所で展開される展示を見終わった際に、なんとなく次のようなことを想像した。曳舟駅を降りて、展覧会場にmapを見ながらたどたどしく歩いている筆者の姿を、実は妖怪たちが、電柱や家屋の屋根の上、そして使われなくなった家の窓の隙間などに隠れながら見ていて、くすくすと笑いながらも、さわの展示へと導いていたのだ、と。
中野仁詞
神奈川芸術文化財団学芸員。近年の主な企画に小金沢健人展「裸の劇場」(2018年)、さわひらき展「潜像の語り手」(2019年)、大山エンリコイサム展「夜光雲」(2020年)、冨安由真展「漂泊する幻影」(2021年)、志村信裕展「游動」(2021年)など。国際展では、第56回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展(2015年)日本館キュレーターとして塩田千春「《掌の鍵》–The Key in the Hand – 」展、ヨコハマトリエンナーレ2017「島と星座とガラパゴス」。女子美術大学、東海大学非常勤講師。