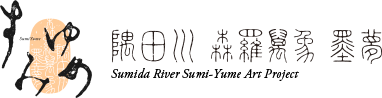10年目を迎えるすみゆめの、これまでとこの先

「隅田川 森羅万象 墨に夢」(通称:すみゆめ)は、2025年で10周年を迎えます。
地域で活動するみなさん、地域や文化に関心を寄せて参加してくださるみなさんの活動をよりよい形で実現するため、事務局のメンバーは主催企画の実施だけでなく、公募によるプロジェクト企画に対する伴走支援も続けてきました。
区切りのタイミングで、これまでのすみゆめを振り返るとともに、この先について考えてみたい。そこで事務局のメンバーが、今、お話を伺いたい方々にお集まりいただきました。
選考委員として活動を見守ってきてくださったセゾン文化財団の久野敦子さんと、東京藝術大学 特任准教授の大内伸輔さん(※)。そして様々なアートプロジェクトに関わってきた美術家の藤浩志さんとともに、すみゆめの魅力やそれを支える事務局のあり方について考えた様子をご紹介します。
※久野さんは2016〜2023年、大内さんは2017年〜選考委員を担当
<プロフィール>
藤浩志
美術家/NPO法人アーツセンターあきた 理事長
1960年鹿児島県生まれ。京都市立芸術大学在学中演劇に没頭した後、公共空間での表現を模索。同大学院修了後パプアニューギニア国立芸術学校に勤務し原初表現と人類学に出会う。バブル崩壊期の土地再開発業者・都市計画事務所勤務を経て土地と都市を学ぶ。「地域資源・適性技術・協力関係」を活用し地域社会に介入するプロジェクト型の美術表現を実践。取り壊される家の柱で作られた「101匹のヤセ犬」、給料一ヶ月分のお米から始まる「お米のカエル物語」、家庭廃材を蓄積する「Vinyl Plastics Connection」、不要のおもちゃを活用した「Kaekko」「イザ!カエルキャラバン!」「Jurassic Plastic」、架空のキーパーソンを作る「藤島八十郎」、部室を作る「部室ビルダー」等。十和田市現代美術館館長を経て秋田公立美術大学教授、NPO法人プラスアーツ副理事長、NPO法人アーツセンターあきた理事長。
久野敦子
公益財団法人セゾン文化財団 常務理事
多目的スペースの演劇・舞踊のプログラム・コーディネーターを経て、1992年に財団法人セゾン文化財団に入団。2017年より現職。現代演劇、舞踊を対象分野にした助成プログラム、自主製作事業の立案、運営を担当。日々、舞台芸術のための新たなインフラ開発、才能発掘、育成のための支援のあり方を模索中。最近は、資金と稽古場の提供を組み合わせた、より効果的な支援方法について思案している。アーツカウンシル東京カウンシルボード、神奈川県文化芸術振興審議会委員、公益財団法人埼玉芸術文化振興財団評議員、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団理事ほか。
大内伸輔
東京藝術大学 大学美術館 特任准教授
1980年茨城県生まれ。2005年より茨城県取手市の取手アートプロジェクトのアートマネージャー養成プログラム「TAP塾」インターン。現在も現場スタッフとしてかかわる。2006年より東京芸術大学音楽環境創造科教育研究助手。2009年より公益財団法人東京都歴史文化財団東京文化発信プロジェクト室(現アーツカウンシル東京)において「東京アートポイント計画」を立ち上げ期より担当。地域に根ざしたアートプロジェクトの担い手となるNPOの育成を行う。2024年より現職。東京藝術大学大学美術館取手館/取手収蔵棟の運営及び地域連携を担当。
岡田千絵
アートマネージャー/(公財)墨田区文化振興財団 地域文化支援課/「隅田川 森羅万象 墨に夢」実行委員会 事務局
1983年大阪市生まれ 大阪芸術大学芸術計画学科卒業。事務局スタッフとして公共空間への一時的な作品設置や、企画実現のための運営についてコーディネートやアドバイスを行なう。アーティストとまちをつなぐ、スタッフと作品の間を補うようなことに気を揉むおせっかいなアートマネージャー 。その時その場所でしか出来ない作品に関心がある。2012~2016年アサヒ・アートスクエア事務局(NPO法人アートNPOリンク)を経て、2017年より公益財団法人墨田区文化振興財団の地域文化支援担当として「隅田川 森羅万象 墨に夢」実行委員会事務局を担当。
(敬称略)
表現を守る伴走支援
岡田:今日はお集まりいただきありがとうございます。2016年にスタートしたすみゆめのこれからを考えるにあたり、みなさんにお話を伺いたいと思っています。
すみゆめはアートプロジェクトとして開催していますが、ここ数年、周りから「アーツカウンシル的な動きをしている」と言われることもあります。私たちが参加団体への伴走支援をしている姿がそう見えるのだと思うのですが、大内さんは2024年までアーツカウンシル東京で、さまざまな団体に伴走支援をされてきましたよね。
大内:そうですね。すみゆめの事務局のみなさんは、多いときで22組、今年度は12組の参加団体に関わってきている。その伴走支援があるとないとでは大違いで。
例えばホールや美術館では基本的な制度やルールがあって、その中で企画を進めることになります。けれどすみゆめに参加する団体の多くが、まちのなかで企画を実施する。可能性や期待も大きいけれど、危険もいっぱいで。チャレンジしたいと思ったときに「それはあの人に聞けばいいよ」「こういう手続きをすれば大丈夫」と相談できる相手がいないことには成立しないことばかりなので。事務局の伴走があることが、すみゆめの価値になっているんじゃないかと思います。
久野:支援する立場にある人は、気をつけないと無意識のうちに権力を持ってしまうことがありますよね。知らず知らずのうちに、支援する側の理想やイメージに合わせるような助言をしてしまうことがある。それは、実はとても注意すべきことなんです。すみゆめの事務局はその点を理解していて、支援対象者がアイデアの壁打ち相手として、どうすれば良いのか一緒に悩み、企画を形にしていくために必要な課題を一緒に解決していく。そこに伴走支援の本質があるのだと思います。
岡田:伴走支援の部分は、事務局3人のうち私がほぼ1人で担当しています。確かに、自分の考えや得意なやり方に無意識に寄せていく危うさみたいなことは意識していますが、その人の表現を守ることとのあいだでゆらゆらすることはあります。
大内:すみゆめの企画は表現のジャンルの幅が広いじゃないですか。地域コミュニティのこと、ソーシャルインクルージョンのことを扱うものもある。わからないことは誰かにつないでいく、ネットワークのハブみたいな役割をしているから実現できていることも多いのではないかと思いますね。
対話できる関係
藤:伴走支援って、具体的にどういうことをしているんですか。
岡田:表向きには美術の施工展示だったり、舞台の音響照明だったり、企画を実施するためのテクニカルな相談に乗ります、ということを謳っています。実際のところはお話を聞いて、広報のためにSNSのフォロワーさんを増やしましょうとか、プレスリリースを書きましょうとか。より良い企画につなげるために、都度都度話を聞いています。公共施設を使うときの手続きのコツみたいなものを共有したり、提出前に書類を見せてもらったりもしていますね。
藤:地域のなかで人のつながりを重ねてきているから、できる役割があるんでしょうね。
久野:私がよく覚えているのは、コロナ禍のことです。あのときは、みんなが「どうしたらいいのかわからない」と困惑していて、参加団体の方々が「これでは実施できない」と頭を抱える状況になっていましたよね。そんな状況の中で、事務局のみなさんがオンラインでの開催という方法を提案して、オンラインに慣れていない参加団体の方々と、実際に一緒にパソコンを触りながらどうすれば実現できるのかを探っていました。事務局から、ただ、提案するだけでなく、実現への道筋を一緒に模索していた姿が印象的でした。
岡田:そうですね。例えば高齢の方々が民話を語るという企画をやっていて。コロナ禍で家から出られないから練習もできない。だったら録画したものを先生に見てもらってアドバイスをいただくとか、YouTubeで発信してみたらどうだろうとか。近いエリアに住んでいるカメラマンを紹介して、なるべく人に会わずに収録する方法を提案したりしました。
藤:それはすごいね。
久野:報告会のとき、その方々が「オンラインを使ってちゃんと事業を実施しました!」と誇らしげに話していたことが私もとても嬉しかったです。困難な状況でも伴走し続けることができる。すみゆめの事務局は、そうやって一つひとつ丁寧に対応ながら信頼を積み上げているんだなと感じました。「やればできる」ことを知っている、そして一緒にやってくれる相手がいるというのは、本当に心強いですよね。
大内:さまざまなアートプロジェクトが軒並み中止になっていくなかで、流れを止めなかったのはすごいことだと思います。どうすればできるか、という対話をし続けられる関係性ができている。特に掲げてはいないけれど、自分たちの力で活動する人が増えていく、育成事業のような側面も持っているように感じます。
持ち寄り、交わす寄り合い
岡田:2021年頃に「Meeting アラスミ! 理論編 新しい文化政策を考える」に参加した際には、伴走支援に加えて、初回から続けている「寄合」にも価値があると評価していただいたことがありました。特に予算をつけずに事務局が動いてやっていることなので(※)、そこに価値があったのか!と驚いたんです。
寄合は、その年の参加団体が決まる6月から報告会がある翌年の2月まで、毎月1回開催しています。採択された団体さん以外にも、地域で活動している方々や過去に参加した方々にも門戸を開いていて。誰でも覗きに来ることができるようになっています。
※2024年度はゲストを招いて勉強会等も実施
大内:運営する際には、どんなことを心がけているんですか。
岡田:発言しやすい状況つくること、必ず少しでも全員が発言できるようにすることです。回を重ねていくと、救急処置のことや広報のやり方、似たお悩み事があることがわかってきました。自己紹介で得意なことを話すようにしてもらったら、寄り合いが終わったあとに参加者同士が声をかけ合って、「これを手伝ってほしい」ってつながりも生まれたりもしています。
大内:参加者同士でリソースのシェアができる仕組みはすごくいいですね。アートプロジェクトにおける学びや課題って、けっこう“あるある”なことが多くて。持ち寄って話せる機会があるのは、すごく効果的だと思います。
藤:寄合のお知らせを届けている先が200件もあるんですね。それって、墨田区に関わる人たち200人に情報を渡すことができるということで。その積み重ねは、すごく大きな価値ですよ。
久野:すみゆめでは、参加を希望する団体から届く申請書を読むのがいつも楽しみでした。アーティストが「表現をしたい」という思いから事業をスタートしている一方で、地域の課題に向き合うことを出発点にしている企画も多い。「防災のためには、平時から人とつながることが大事」という問題意識からイベントが発想されたり、普段の生活の中から、表現がうまれたりしている。そうした多様な活動が共存していることが、とても重要だと思います。
岡田:近年はアーティストの活動の割合が増えてきて、地域の団体さんからは「私たちにはアートが思いつきません」とか言われたりするんです。でも、地域のみなさんから出てくる発想は、アーティストにはできないものだったりして面白いんですよね。さまざまな人が参加できる状況は、これからも続けていきたいです。
芸術祭とすみゆめ
岡田:10周年を迎えるにあたってネクストすみゆめを考えると、残すべきことと変えるべきことがあると思っていて。実は、墨田区では2026年から「総合的芸術祭」を開催する動きがありまして。どうせなら、すみゆめもそのタイミングで、いつもはできないようなことをする機会にできたらいいなとは話しているんです。たとえば各団体が使える予算を大きくしてみるとか、テーマを広くしてみえるとか。そういうトライアルなタイミングにできたらいいねと。
藤:芸術祭がどんなものになるのかにもよるけれど、飛距離をどうするかという考え方もありますよね。どこまで届けるのか、海外から呼びたいのか自分たちが楽しみたいのか。
大内:すみゆめではここ数年、墨田区外からの応募が増えていますよね。あの場所ならなにかできそうだとアーティストが集まってくる。新陳代謝があって、入るときには地域とつないでくれる人がいる。オーディエンスもわざわざ遠くから呼ばなくても、暮らしている人たちが「またこの時期になにかあるだろう」ってことがわかっていて、気になったら参加できちゃう。そういう仕掛けや距離感は、すみゆめで培ってきたいい雰囲気だと思うんです。
久野:以前、墨田区の部長さんのお話で「すみゆめの企画は、隅田川周辺であれば、必ずしも墨田区内でなくてもいいんです」というご発言がありました。つまり、隅田川、北斎にまつわる地域で文化を育んでいこうとしている。「文明の発祥の地が川のあるところから始まっているように、“隅田川文明”をつくっていくんだ」という話もあって、私はそれに感動したんです。
この10年で地域の人たちと丁寧に築いてきた信頼関係は、決して手放してはいけないものだと思います。大規模な芸術祭のようなイベントと、すみゆめのように地域に根ざしたプロジェクトとが、うまくバランスをとりながら続いていくといいですよね。
大内:すみゆめの企画って、墨田区の行政の方がちゃんと現場に見に来てくださるのがいいんですよ。現場の人たちの顔を見て、会話をして、自分たちも楽しめる距離感と関係性ができている。すみゆめを経験してきた地域で始まる芸術祭は、他とはまったく異なるものにできるんじゃないかと思います。
藤:大きなことが起きると、その周りに組織なり場所なり、いろいろなものが出てくる。最近は大きなプログラムって、周りの小さなことを生み出すためにあるんじゃないかって思うくらいで。それをきっかけに、つくり手が集まってくるんですよね。
僕は、自分が活動をつくりたい人だから。どうすれば圧倒的な表現ができるのか。そのためにどういうフィールドがあるのか、どういう状況が生まれたときに活動が出てくるのかっていうことに興味があるんです。圧倒的に面白いことができると、また次の動きが出てくるじゃないですか。予想がつかないプログラム、今あるものとはぜんぜん違うタイプの表現も出てきていいんじゃないかっていう気がしていて。有象無象が出てくる機会をつくれたら面白いですね。
そして、そのような多様性や、普段は足を踏み入れられない場所をたくさんのツアーで見てもらうような形式も、すみだらしい芸術祭になる気がします。
事務局のカタチ
岡田:今とは違う表現ということで言うと、分野の違うアートマネージャーを増やしていかないと、どうしても得意なところを扱ってしまうというか、新しくなれないとは思っています。人数的にも1人ですべての活動を手取り足取りサポートすることはできないので、いい距離感、自立しやすい距離感を探ってはいます。とはいえ、蓄積してきた情報を必要なときに引き出せる状態になっているかというと、どうなんだろうと。
大内:属人的になってしまうと、その人がいなくなったとき、蓄積してきたものがゼロになってしまいますよね。スキルをチーム、組織として持っていることが大切だと思います。
藤:いかに分散していくかが、重要かなと思っていて。10年やっていれば、地域のなかにいろいろな活動を続けている人が出てきているはずで。その人たちの専門分野で支援やサポートができるよう、委譲してネットワークをつくっていくというのはどうでしょう。参加側のネットワークだけではなくて、運営側のネットワークみたいなものを構築していく。
岡田:確かに、運営側のネットワークづくりというのは考えたことがありませんでした。
久野:最初は地域の方々による活動が中心だったところにアーティストたちが加わってきて、そこに化学変化が起きたんですよね。住民にとってもアーティストにとっても、互いに刺激と気づきがあって、奇跡のような関係性が生まれている。ここまでうまくいっている事例って、そうそうないと思うんです。だからこそ、この10年で培ってきたものを大切にしながら、次の形を模索していけるといいですよね。
大内:伴走支援をするなかで、関わる人たちにインストールしてきたマインドってあると思うんですよ。事務局が関わった人たちが手渡したノウハウが、枝葉のように伸びていって、新しい活動につながっているはずで。関わった人たちがその後、こんな活躍をしている、というのを追ってみてもいいかもしれません。きっと、成果として見えてくるものがあるはずです。
岡田:まだまだできることがたくさんあると、改めて感じることができました。ありがとうございます。すみゆめはその時々で、さまざまな人と対話しながら可能性を拡げてきました。これまでの積み重ねを活かして、おもしろそうな場所や人が交わったり、開かれていくような伴走支援をけたいと思います。これからのすみゆめも、引き続き見守っていただけるとうれしいです。