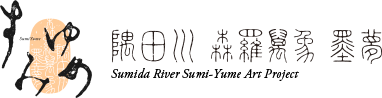風は吹いているか? 内への凝縮、外への開放『ほくさいゑとき ―義太夫とコンテンポラリーダンスによる―』【2020年イベントレポート】
 撮影:川瀬一絵
撮影:川瀬一絵山道弥栄が構成・詞章・作曲・演出、安部萌が振付・出演した『ほくさいゑとき -義太夫とコンテンポラリーダンスによる-』を観た。これは2020年12月末から1月上旬にかけてオンライン配信された舞踊作品で、葛飾北斎が晩年(1835〜36年頃)に手掛けたとされる錦絵の連作「百人一首姥がゑとき」を軸に、能、日本舞踊、バレエの所作、能『歌占』、能『檜垣』、近松門左衛門『雙生隅田川』などに登場する和歌のフレーズをコラージュ、音楽的に言えばリミックスして構成されている。この手法について、作品本編の前説動画で山道は次のように解説している。
本歌取りは、ある種、古典へのアンサーソングなのではないかと思っています。北斎も一個人のおばあちゃん(姥)の視点を通して、江戸の当時の感覚から百人一首をもう一度見つめ直してみるとこうなった、という彼なりのアンサーを作品に込めたのではないかと考えました。「百人一首姥がゑとき」には、本歌の時代、百人一首が選定された時代、北斎が生きた時代、いろいろな時代が共存しています。たくさんの時代の層が木版の重なりのようにも感じられて、北斎の二次元の世界を立体的にしたいと思いました。
「本歌取り」とは、既存の古歌の一部分を引用し、自作に取り入れる和歌の表現技法の一つで、作家個人のオリジナリティ、独創性に重きを置く近代的な価値観と、日本で発達した古典の価値観の相違を端的に示している。この発想を援用して『ほくさいゑとき』はつくられた、ということが最初に共有しておきたい前提だ。
筆者は古典芸能に詳しいわけではなく、オタク的な考察厨でもないので、作品の細部について「これはあれで、あそこはそれで」と解析するようなテキストは書けないが、そんな自分でも「お」と思うぐらいに、『ほくさいゑとき』は明確に「百人一首姥がゑとき」の諸風景を引用している。
例えば前半。あぐらをかいて座り、焚き火にあたって頬杖をついたり、うつぶせに寝そべって両足をぱたぱたと動かす所作は、大中臣能宣(おおなかとみのよしのぶ)の歌、
みかきもり 衛士のたく火の 夜は燃え 昼は消えつつ ものをこそ思へ
……を描いた一枚に登場している衛士の姿そのものであったりする。つまり、ある時代の、ある人物(この場合は北斎)の視点を通してかたちになった風景の再現としての舞踊を目指す、というのが『ほくさいゑとき』のダンスドラマトゥルギーであろう。
本編に続いて観た山道と安部萌によるアフター座談会では、後半のあるシーンが新型コロナウィルスの感染拡大と、それによる人々の気持ちの落胆を描いていたことが明かされる。身体のなかにウィルスが侵入し、発熱してマスクをつけ、他人とディスタンスを置こうとして、部屋に閉じこもる……この一連の所作は、現代を生きる2人の視点がとらえた風景であり、先に紹介した「本歌の時代、百人一首が選定された時代、北斎が生きた時代」のさらに先にある2020〜21年の日本の風景が、「古典へのアンサーソング」として新たにコラージュされているということだろう。
これらを踏まえたとき、当然思い出されるのは「木ノ下歌舞伎」を主宰する木ノ下裕一の補綴(ほてつ)と呼ばれる作劇手法である。補綴とは本来、台本の作成作業、とくに既存戯曲の再編集作業を指すが、木ノ下の仕事はそこに留まらない広がりを見せる。緻密な文献調査や作品にまつわる土地のフィールドワークを行い、得られた知識をもとに上演の構成の全体設計図を作成。さらに、それらに先行するかたちで作品を演出する演出家の指名が木ノ下からなされる(これも補綴の範疇と捉えるかは微妙だが、木ノ下歌舞伎作品においては非常に重要な作業だ)。
連関し合いながらバラバラでもあるこういった要素を結び合せる作業は演出家と木ノ下の合議によって決定されていくようだが、大きく言えば、木ノ下が夢見た「世界」を多角的に組み立てていく仕事の総体を「補綴」と呼ぶのがふさわしいだろう。
山道は木ノ下歌舞伎のメンバーでもあるので、木ノ下の補綴思想の影響を少なからず受けているはずだが、共通する点がある一方で、古典に対するアプローチとして決定的に違う部分もあるように思われる。アフター座談会から引用する。
安部 (山道は)古典のなかにいる女の子をピックアップして、その子のことを思って、ストーリー性のある作品をつくっている。今回はタイトルにもあるように北斎を扱っている。
山道 浮世絵も好きだから、葛飾北斎の作品からつくれないかなと思った。でも北斎は「富嶽三十六景」が有名で、風景を切り取るのが得意な作家という印象が強くて、あまり魅力を知らなかったから、そこに壁があった。
たしかに多くの山道作品では、キャラ化された「少女」を軸に、その架空の少女と接続しうる、古典の振付、歌、物語を引用し、コラージュしていく手法が採られている。
例えば東京都がコロナ禍での芸術文化活動支援事業として実施した「アートにエールを!」の枠でつくられた『うつをみ』(2020年)。同作は日本舞踊を学んだ経験を持つダンサー・振付家の中川絢音とのコラボレーション作品で、山道は作曲と詞章の提供を行なったに留まるようだが、ここから山道作品の特性を敷衍することも可能だろう。
後白河法皇の娘・式子内親王と歌人・藤原定家の秘められた恋のゴシップを扱った能『定家』を題材にさまざまな和歌の一節をコラージュした同作は、羽織姿とピンク髪が印象的な中川の身体にさまざまな物語素や類型がインストールされることで、舞台の時空間にさらに新たなキャラクター像を受肉していく印象を抱かせる。
後日、山道から提供された『ふることふみ −義太夫とコンテンポラリーダンスによる−』(2019年)、『酒呑童子 −義太夫とコンテンポラリーダンスによる−』(同)などにも通じる個人の身体的・精神的な経験とその変容のリアリティを重視するあり方はそもそも舞踊のジャンル的特性でもあるが、山道作品と木ノ下歌舞伎とのもっとも大きな差異でもあるだろう。木ノ下が世界観構築のために補綴のプロセスを展開していくのとは逆に、山道はダンサー個人の内側に向けてさまざまな情報を凝縮し、統合された人格を生み出す作業として「補綴的なるもの」をとらえているのではないだろうか。
だからこそ『ほくさいゑとき』では、キャラ化されたような歩き巫女や白拍子が冒頭と末尾を飾るのであり、彼女が北斎の描いた百人一首世界やその平行世界としての和歌や能をランダムに巡っていくような、多元SF的な旅の印象を強める。
以上がおおまかな『ほくさいゑとき』の雑感だが、最後に衣装について触れておきたい。この原稿執筆の依頼を受ける前から、筆者はおそらくSNSで本作の映像を断片的に目にしていた。そのとき記憶に残ったのが、藤谷香子が制作した衣装である。藤谷は「快快 –FAIFAI-」のメンバーだが、さまざまな作品で活躍するスタイリスト(衣装)としても知られる。とくに岡田利規作品における仕事は秀逸で、演出や演技では描写しきれない作品の空気感や襞(ひだ)を衣装の細かいディテールで具現化してみせてきた。
『ほくさいゑとき』の構想段階で、山道がどのようなオーダーを藤谷に送ったかは定かではないが、白い衣装とビニール生地の半透明の袴は現代的な白拍子をイメージしたものだろう。だが、初見時に筆者が真っ先に連想したのは韓国舞踊のチマチョゴリだった(後ろでまとめた髪型も影響)。日本の芸能文化の源流が朝鮮半島由来、大陸由来なのは周知のとおり。そして筆者は藤谷の衣装から、作品の「外」から吹き込む風を感じた。それは個人的な楽しい誤読ではあるのだが、『ほくさいゑとき』から筆者が感じたある種の生真面目さ・生硬さを解きほぐしていく役割を衣装が担っていたことは疑いない事実だと思う。
古典を扱う現代作品は、古典ファンに目配せするためのオタク的知見の開陳が悪目立ちすることがしばしばある。それは「沼にはまる」と表現されたりする作品受容のスタイルの深化、作品の質的・興行的な安定を生み出しもするが、行き過ぎれば作品・作家と観客の関係性を固定化してしまう危うさもある。
藤谷の衣装が喚起する誤読は、外に向けて穿たれた風穴かもしれない。そこから流れ込んでくる外気は作品を生き生きと揺らすだろうし、内から外へと流れ出す作品の空気は、外の世界を豊かにしていくだろう。趣味性に自閉するだけではなく、さまざまに開かれた作品であってほしい。『ほくさいゑとき』を観てそう思った。
島貫泰介
美術ライター/編集者。1980年東京生まれ、京都在住。『CINRA.NET』『美術手帖』などで執筆・編集を行うほか、企画も行う。またリサーチコレクティブチーム「禹歩」として捩子ぴじん、三枝愛とともに活動中。2021年度は大分県別府市の清島アパートに滞在。いろんなことをやってます。